群馬工業高等専門学校 Lasermeister 100A 導入事例(1)
Lasermeister 100A
2025.07.17
こちらの記事は2回シリーズです。初回はこちらからどうぞ
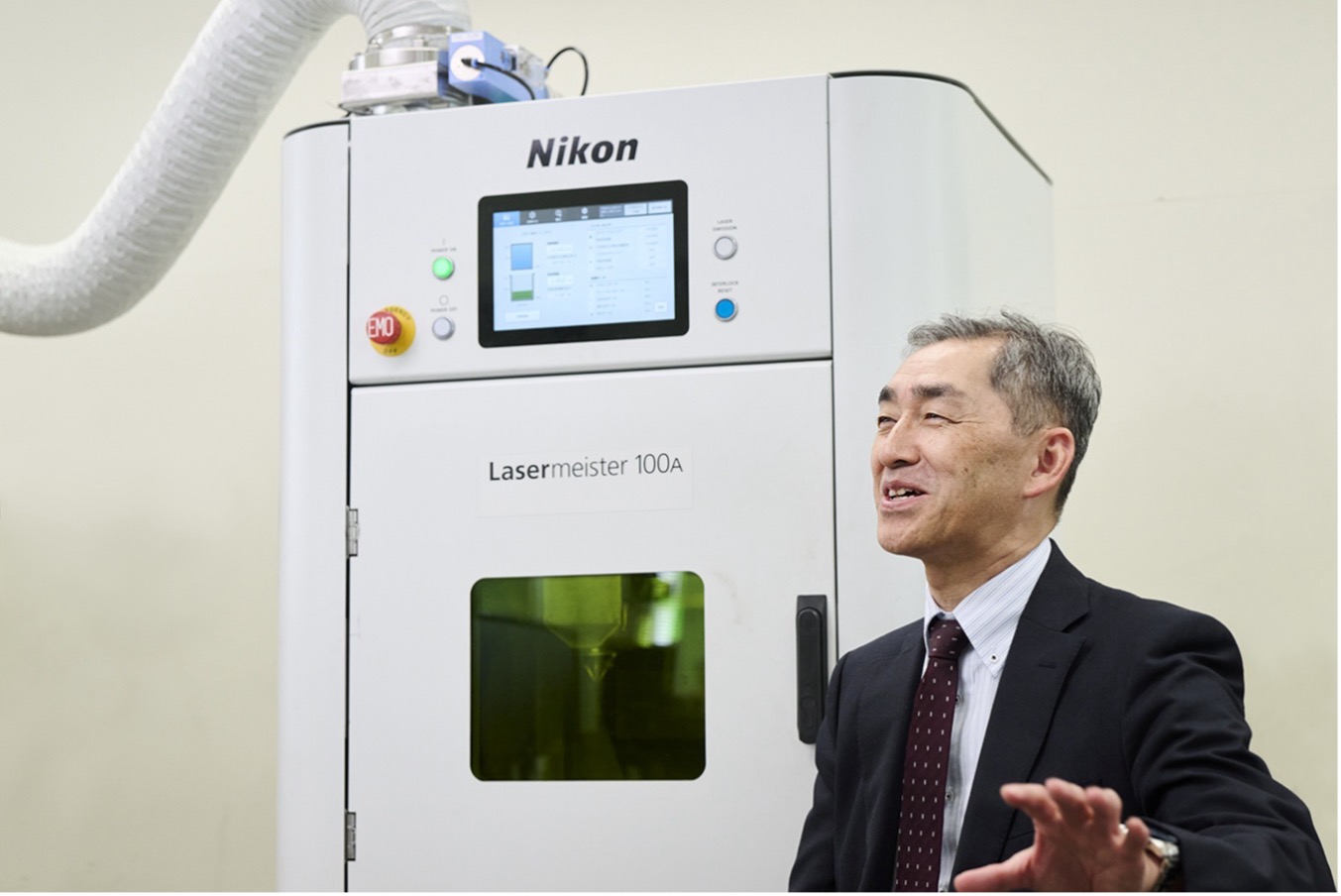
群馬県前橋市の群馬工業高等専門学校(以下、群馬高専)では、ニコンとの共同研究の一環として、2018(平成30)年から光加工機「Lasermeister 100A」をご導入いただき、実習をはじめ、卒業研究、中学生を招いての体験授業など、幅広い用途にご活用いただいています。
群馬高専の特色やLasermeister 100A導入に至った経緯などについて、機械工学科教授の黒瀬雅詞先生にお話を伺いました。
座学と実学のハイブリッド教育で、即戦力として活躍できる人材の育成を目指す
──群馬高専の概要について教えていただけますか?
黒瀬先生:本校は一般に「高専」と略されることが多い高等専門学校の一つで、国立の高等教育機関になります。中学校を卒業した者に入学資格があり、実践的かつ創造的な技術者の養成を目的に5年間の一貫教育を行っています。現在は機械工学科、電子メディア工学科、電子情報工学科、物質工学科、環境都市工学科の5学科構成で、学生数は1000名ほどです。卒業時には準学士が授与されます。1995(平成7)年からはより高度な専門研究を行う2年制の専攻科が追加され、学科卒業後も引き続き本校で学べるようになりました。こちらは生産システム工学専攻と環境工学専攻の2構成で、学生数は60名ほどです。修了時には大学卒業に相当する学士(工学)の学位取得が可能になります。教員については1学科あたり約9名で、一般教科の担当も含めると85名ほどが在籍しています。

──日本で初めて設立された高専だとお聞きしました。
黒瀬先生:はい。本校は、1962(昭和37)年に日本初となる国立の高専として開校した「1期校」と呼ばれる12校のうちの一つでもあります。群馬県には戦前、自動車メーカーのSUBARUの前身となる中島飛行機株式会社という航空機メーカーが工場を構えていて、高崎と前橋の間に飛行場がありました。戦後、桑畑になっていたその飛行場の跡地を活用して産業の基点を作る話が持ち上がり、高崎と前橋、そして群馬町(現在は高崎市に編入合併)の交点に本校を設置することが決まったのです。当初は土木工学科、機械工学科、電気工学科の三つの学科でスタートしましたが、後に群馬県では織物産業が盛んなことから化学へのニーズが高まり、1966(昭和41)年に工業化学科が増設されることになりました。さらに、1987(昭和62)年には情報系の学科の追加が決まり、現在まで続く5学科構成になっています。私が着任した1995(平成7)年には、学士課程となる機械系と環境系の二つの専攻科が新たに加わりました。
──ご着任から30年になるのですね。黒瀬先生のご経歴についても教えていただけますか?
黒瀬先生:恐竜博物館で知られる福井県勝山市の生まれで、金沢大学の教育学部で小学校の教員養成課程に入りました。実は小学校の先生になりたかったんです。副免として中学校技術の教諭免許も取得しましたが、バブル崩壊や就職氷河期と重なってしまったこともあり、就職はせずに博士コースに進んで、当時設置されて間もない自然科学研究科で第1期生のドクターになりました。卒業後はどこかの大学に入ろうと思ったのですが、なかなか見つからず、半年ほどオーバードクターをした後、1995(平成7)年に群馬高専に着任しました。もともとの専攻は中学技術で、木材加工や金属加工、情報について学び、金沢大学では木材加工の非常勤講師も務めていました。博士コースでは破壊力学を専攻し、金型や材料の強度に着目していたので、そこから設計や3Dプリンターの強度といった今の話にも結び付いているわけです。
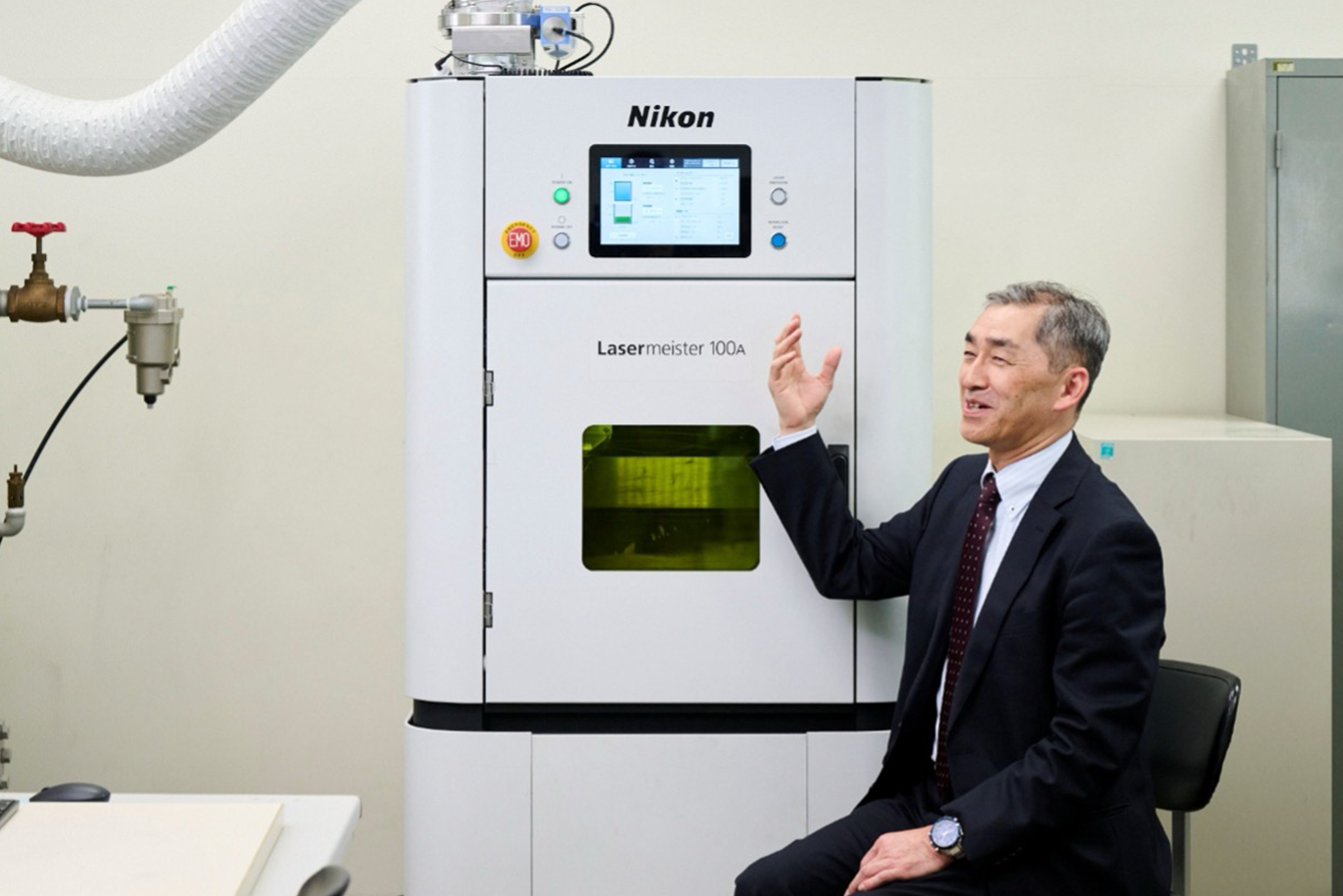
──群馬高専の教育方針とはどのようなものでしょうか?
黒瀬先生:国立の高専を設立するにあたり、単なる座学だけでなく、実学も合わせて学ぶことで、卒業後すぐに技術者として社会に出て働ける人材を育てようという狙いがありました。そこで本校では、座学と実学をハイブリッドで学ぶことにより、即戦力として活躍できる実践に強い人材の育成を目指しています。中学校を卒業後、本校に入学してすぐに実学を学び始めるわけですが、実学だけを重点的に学ぶのでは、工業高校と同じになってしまいます。そこで、座学についてもしっかりと勉強し、原理・原則を理解した上でさまざまな加工が行える技術を身につけられるよう、独自のカリキュラムが組まれているのです。
具体的な授業の内容としては、まず1〜2年生の低学年では他の学科との混合学級で工学分野について広く学びつつ、一般高校の科目と実業高校の科目をこなしていきます。混合学級の制度が始まったのは2006(平成18)年からです。中学を卒業したばかりの学生を最初から専門分野別に完全に分けてしまうのではなく、まずは大きな括りでいろいろなことを幅広く学んだ上で、自分の専門学科に分かれていくスタイルに変えたわけです。この制度が功を奏し、学科の垣根を越えて幅広い分野の知見を持った学生を育てることができていると感じています。SDGsといった時代の流れもありますが、機械工学科でも環境に注目しながらものづくりに取り組む学生が育っていますし、卒業後に土木工学に進む学生もいます。
その後、3年生に進級してからはそれぞれの専門学科に分かれたクラス編成となり、大学と同等の専門的な領域について学んでいきます。ちなみに、本校のように高学年に進むほど専門科目の割合を増やしていく教育方法を「くさび形教育」と呼んでいます。
──卒業後の学生の進路はどのようになっているのでしょうか?
黒瀬先生:各学科の学生のうち10名程度が就職を選択し、1〜2割が地元や関東圏の企業に入っています。特に土木系の学生は県庁や市役所など、行政職に進むことが多いですね。残りの学生は進学を選択して、7名程度が本校の専攻科に、20名程度が外部の大学にそれぞれ進みます。そのうち、8〜9割が大学院まで進学していますね。特に機械工学科は優秀な学生が多いこともあり、大学院まで進むケースが少なくないです。数年前まではコロナ禍の影響もあり、学科を卒業してもすぐには就職せずに進学して、状況が変わるのを待つ傾向が強かったようですが、最近は就職を選ぶ学生も徐々に増えてきたところです。
──Lasermeister 100Aを使用している機械工学科について教えていただけますか?
黒瀬先生:機械工学科では、1年生から3年生にかけて、工作機械が並んでいる実習工場と呼ばれるスペースで工作実習の授業を受けます。週の半分で実習を行い、残りの半分でそのレポートを作成するという流れで、かなりの時間をかけて実際に機械を使用したものづくりが体験できるようにしています。汎用機械から始めて、最終的にはNC加工機も扱えるようにCAMなどのNCプログラミングについても学びます。
設計・製図に関しては、1年生で手描きの製図、2年生で2次元CAD、3年生で3次元CADと段階的に学び、4年生からは機械設計法と総合設計に取り組みます。総合設計では、私が着任した頃は手描きや2次元CADを扱っていましたが、3次元CADの導入後は全員がプログラミングと設計計算、さらにはCAEまで習得するようになりました。モーション解析も実施させ、各部品がかみ合ってきちんと動くのかを確認するなど、実際に動くものを作り出すように指導しています。2012(平成24)年からは石こうタイプの3Dプリンターを導入し、実際に部品を製造して組み立てる工程も加わりました。ただ、当時の石こうプリンターは正確な寸法で出力することがなかなか難しく、歯車が楕円形に仕上がってしまうこともありましたね(笑)。その後、樹脂プリンターを導入してからは、ある程度は真円の部品が作れるようになりましたが、それでも精度が高いとは言えません。高精度な製品を作ることの難しさを学生が実体験をもって学び、ものづくりに真摯に取り組むことの重要性を認識するきっかけになったのではないでしょうか。
ちなみに、以前は個人単位で課題に取り組ませていましたが、近年は少人数グループによるチームベースドラーニングを採用しています。プレゼンテーションも含めた競技形式とすることで、学生同士でお互いに評価し合えるようにしました。Lasermeister 100Aの導入以降は、卒業研究に進む前段階として、Lasermeister 100Aでさまざまな作品を作製し、自分たちでプロモーションビデオを作るなど、事業化を目標とした設計資料の作成も含めた課題を出しています。設計の趣旨を自分たちで考えたり、金属プリンターを活用しながら強度を考慮した設計に取り組んだりすることで、CAEを通じてものづくりの難しさや楽しさを、じっくり1年間かけて学んでいきます。この課題はニコンさんとの共同研究の一環にもなっているのですが、学生たちにとってもかなり達成感があるようです。

サイズ、性能、安全性の全てにおいて、教育現場に最適なLasermeister 100A
──Lasermeister 100Aをご導入いただいた経緯について教えていただけますか?
黒瀬先生:金属プリンターには以前から興味を持っていて、学会などでいろいろと情報収集をしていました。まず、焼結タイプの金属プリンターは収縮率が大きく、かなり手間がかかる印象がありました。当時はパウダーベッド方式が主力製品として発売されていましたが、こちらについても、教育現場で大量の粉体が消費しきれるのかが疑問でしたね。ランニングコストの問題に加えて、切粉を産業廃棄物として処理する必要が生じるため、環境の観点から見ても教育現場にはふさわしくないように感じました。そこで注目したのがDED(Directed Energy Deposition)方式です。当時、他社さんでDEDと切削加工を組み合わせた装置が発売されていました。切削に関しては学生もかなり使い慣れていて、そこにDEDの付加造形技術が加わるということであれば、導入時に混乱も少ないのではないかと考えたのですが、価格が数億円もするという話でした。さすがにこれは無理だなと諦めていた頃、ニコンさんで同じDED方式の装置を開発しているという話を聞きました。当時はLMD(Laser Metal Deposition)方式という呼び方をしていましたね。いろいろ調べてみると、これがサイズ的にも教育現場にぴったりなんです。こんなに小さな装置を作れるなんて素晴らしい技術力だなと注目していたところ、ニコンさんの方から「このような装置があるのですが、群馬高専さんで使ってみていただけませんか?」とお声を掛けていただきまして、まさに願ったりかなったりという話になったわけです(笑)。
──導入の決め手となった点は、どのようなところでしょうか?
黒瀬先生:教育現場においては、対象物が小型であること、造形過程が見えること、そして安全な環境であることが求められます。これら全てを満たす装置として、DED方式は最適なのではないかと考えていました。そんな中でLasermeister 100Aが発売されることを知り、さっそくどのような仕様なのか調べてみたわけです。以前から使用していた石こうタイプの3Dプリンターはパウダーベッド方式で、造形しながら埋まっていくため、途中の過程が分からない状況でした。DED方式では出来上がっていく様子を見ながら、造形している箇所を確認することが可能です。しかも、Lasermeister 100Aにはカメラも搭載されているので、メルトプールを見たり、表面の状態を確認したりしながら造形できます。これは教育現場にとって非常に優れた点だと思いました。安全性についてもしっかりしているようで、これはいいなと考えていたところ、就職関係を通じてニコンさんからLasermeister 100Aを使用した共同研究のお誘いを頂いたわけです。ちょうど金型造形の研究に取り組んでいたこともあり、教育的にもアプリケーション的にも非常にありがたい話であったことから、装置の導入話がトントン拍子に進んでいきました。
ものづくりに対する学生の探究心を刺激するLasermeister 100A
──Lasermeister 100Aを教育現場に導入することについて、どのような意義があるとお考えでしょうか?
黒瀬先生:3D CADはあくまでも机上の空論に過ぎず、実際には組み立てが不可能なものもできてしまいます。3Dプリンターの登場によって、モニター上で見ているものと実物の違いが明確になり、学生たちの寸法精度に対する意識がより高まりました。そんな中、Lasermeister 100Aの導入によって、より高精度で強度がしっかりと保てる部品を作れるようになったことは、教育現場において、とても意義のあることだと思います。
例えば、歯車を作る場合、除去加工を行う工作機械は非常に高価で台数が少なく、加工にも時間がかかってしまいます。それが現在の3Dプリンターが家庭に1台というような時代になり、形だけなら誰でも手軽に作れるようになりました。しかし、樹脂プリンターではいろいろと厳しいところがあります。単に形にしてゲーム感覚で組み立ててみても、実用性という点では強度が足りずに軸が折れてしまったり、ベアリングが組めなかったりするわけです。その点、強度をしっかり保った状態で数値通りのものが作れるLasermeister 100Aのような金属プリンターの導入は、学生たちにとっても本当にうれしい話でした。とても良い刺激になったようで、スケルトン構造の歯車を作製したり、ブレーキとなるつめ車を加工したりと、学生の方から積極的にさまざまなアイデアを出してくれるようになりました。樹脂プリンターで見た目だけの部品を作って終わるのではなく、金属プリンターで実際に使えてより良いものを作る。実学を追求する高専だからこそ、工作機械の一つとして、Lasermeister 100Aが学生の学びを後押しする力を発揮してくれているように感じています。


